イリノイこぼれ話
 ジャングル
ジャングル
アプトン・シンクレアの小説「ジャングル」の最終章の最後、つまり小説の終わりは、日本で初めて英語を習った中学生でも分かる、同じ簡潔な短文が3回繰り返されています。Chicago will be ours! Chicago will be ours!
CHICAGO WILL BE OURS! ―最初は普通の活字で、2度目はイタリック体で、そして最後は大文字の太字です。著者の熱い熱い思いが渦巻き、鳴門となり、やがて読者を飲み込み、巨大な潮流となることを暗示するかようなエンディングです。「シカゴは必ず我々のものとなる!」 我々って誰。
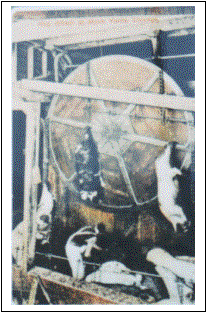
「ジャングル」はシカゴを一番よく表現していると言われる小説です。舞台はシカゴ市南部にあった広大な475エーカーのユニオン・ストックヤード。毎日、鉄道で西部から大量の牛や豚が運ばれてき、隣接している50の屠殺工場でまたたくまに殺され、缶詰加工されて、世界中に輸出されていきました。1865年から閉鎖された1971年までに殺された家畜の数は10億頭をくだらないと言われています。小説は、屠殺・加工工場で働くリトアニア移民家族の悲惨な生活を描きます。読んでいると、宙づりになった豚が天井から吊り下げられた巨大なのこぎりに触れる瞬間に発する短くも鋭い断末魔の声が聞こえてき、鼻をつく獣の死臭が血と汚物にまみれた体にまとわりつき、満足に食べることもできないまま、一日18時間立ちづめ、働き続けねばならない身体は感覚を失い硬直、有害な粉塵を吸い込んだ肺からは咳がとまらなくなる、って感じです。
死と隣あわせの劣悪な労働環境と極貧生活の記述に「日本(人)」も言及されています。一つは、生活の糧を失った貧しい女たちの最後の常套手段、売春宿のひとつに日本人女性が大勢集まっていると。もう1つは、小説の主人公が最後に見出した希望―社会主義に触れ、日本でもすでに社会主義新聞が発行されていると。1903年に幸徳秋水らが始めた「平民新聞」のことでしょう。1906年発表の小説の中で、なぜシンクレアは「日本」を持ち出したのか。

「ジャングル」は、カンサス州ジラード市で発行されていた、当時の世界最大の週刊社会主義新聞「アピール・ツー・リーズンAppeal to Reason」の連載小説として始まりました。「アピール・ツー・リーズンAppeal
to Reason」の記者の一人は、1905年頃に日本人社会主義フェミニスト、金子喜一と結婚するジョゼフィーン・コンガーです。コンガーは、1904年に「平民新聞」に寄稿、自らが社会主義思想の洗礼を受けたミズーリ州のラスキン・カレッジで、熊本出身の留学生、大石善喜と出会ったことを記しています。シンクレアも、どこかの誰かから、はるか遠く太平洋の対岸の話を聞き、日本や日本人を身近に感じていたのでしょうか。ジャングルだなあ、人の輪は。

利潤追求のためには、病気で死んだ動物の肉でも平気で缶詰にした大企業家たちの飽くなき欲望と執着、英語ができず、異国の地で騙され続けながら、体だけが資本だった移民たちの呻きと絶望が、2000を超える囲いの中に閉じ込められた10万頭を超える動物たちの上で交錯した世界こそが、シカゴを大都市にのしあげたわけですが、100年後、そんな生臭く冷血な「ジャングル」を感じたくて、ストックヤード跡を訪ねてみました。
パーシング通りと47番通りのあいだ、地図には、つい30年ほど前まで動物の大量輸送を担っただろう多数の鉄道の引込み線が記されていますが、あたり一帯は空白です。かつての「ジャングル」は今や無機質な倉庫群に変貌し、牛の頭を飾るゲートと「パッカーズ・アベニュー」という通りの名だけが、かろうじて残された「ジャングル」の残滓に思えたのですが。。。
 スーパーに行けば、大手食品会社“オスカー・マイヤー”の各種ハムやベーコンが売られています。ババリア移民だったオスカー・マイヤーは、「ジャングル」でソーセージの作り方を学んだのち、自分のビジネスを始めたとか。
スーパーに行けば、大手食品会社“オスカー・マイヤー”の各種ハムやベーコンが売られています。ババリア移民だったオスカー・マイヤーは、「ジャングル」でソーセージの作り方を学んだのち、自分のビジネスを始めたとか。
日本人選手も活躍する野球場の近く、人通りがない寂れた大通りに取り囲まれたかつての「ジャングル」。道の両側には、窓という窓のすべてに板が打ち付けられた、くずれかけた大きな建物が次から次へと続きます。繁栄と貧困という100年前の大都市シカゴの光と影は今だに健在です。
経済的効率だけを追求し、「負け犬」「負け組」といった言葉が闊歩、働けども働けども貧困ラインから抜け出せない“ワーキングプアー”問題が浮上しはじめた現代の競争社会と、シンクレアが描いた100年前のリトアニア移民の世界とどれほど違うというのでしょう。「CHICAGO WILL BE OURS! 」―明治日本人をも魅了したこの言葉は、今も真摯な響きをもって、読む者の胸に迫ります。